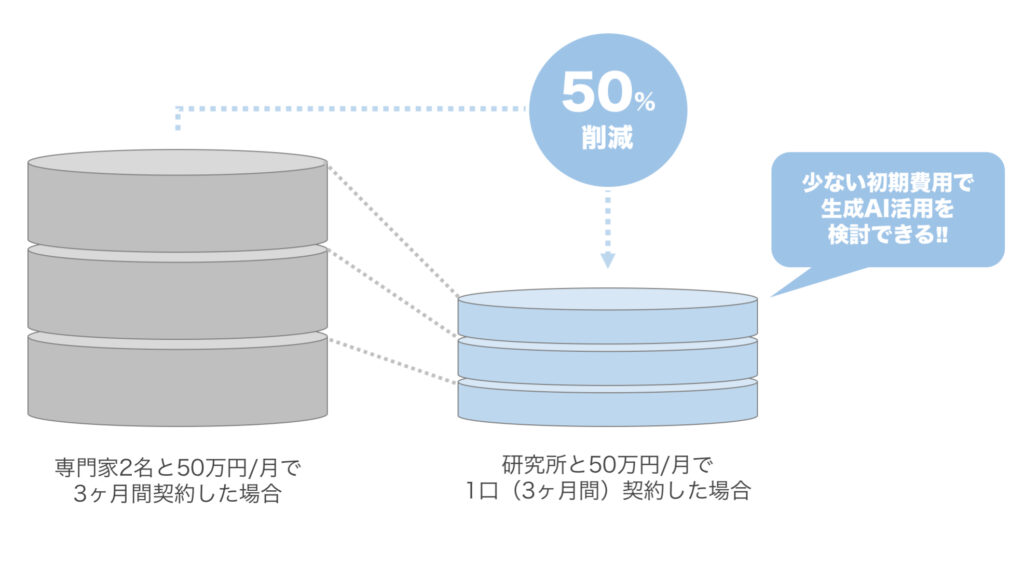Yokohama Generative AI Lab
現在、世界中の企業が
生成AIを用いた業務効率化、成果品質向上、
コスト削減に成功し、
新しい価値の構築、新時代のビジネスの開拓まで
その影響は広範囲に及んでいます。
ビジネスにおける生成AIの利活用には、
「汎用ツールの活用」(例:AIチャットサービス)
「専門サービスの導入」(例:AIエージェント)
「独自開発」
など、さまざまな形があります。
企業の成長戦略において、
これらをどのように組み合わせ、どう活かすかが、
今後の競争力を大きく左右します。
一方で、生成AIの導入に踏み切れない、または
ごくわずかな業務改善にとどまっている企業もあります。
その多くが、
目的設計・データ収集・人材育成・リスク管理など
生成AI導入における初期の壁が
クリアできないことに起因しています。


われわれは、
“生成AI開発における初期の不確実性を明らかにし、
企業の投資判断をサポートすること“を目標に
“横浜生成AI研究所“を創設いたしました。
研究の流れ
- 依頼/スポンサー登録
- 依頼企業はスポンサーとなり、研究テーマを登録します。
- 研究
- 研究所で調査研究を開始します。
研究員はテーマを細分化し、一つずつ深掘りしていきます。
それらを集約・分析し、総合的に検証します。
- 結果報告
- スポンサー企業には定期/不定期に報告会を実施します。
実現性が見えてきた段階で、PoCや開発の委託契約に移行します。
(派遣契約の場合もあり)
研究のメリット
- 検討段階から支援
-
社内での実現性調査にかかる人員や工数を削減し、最小限の負荷で生成AIの導入を検討できます。
- 安価な初期費用
-
常駐型派遣等で専門家に検証してもらう場合、最初から高額になりますが、研究所を利用する場合、比較的安価にスタートできます。